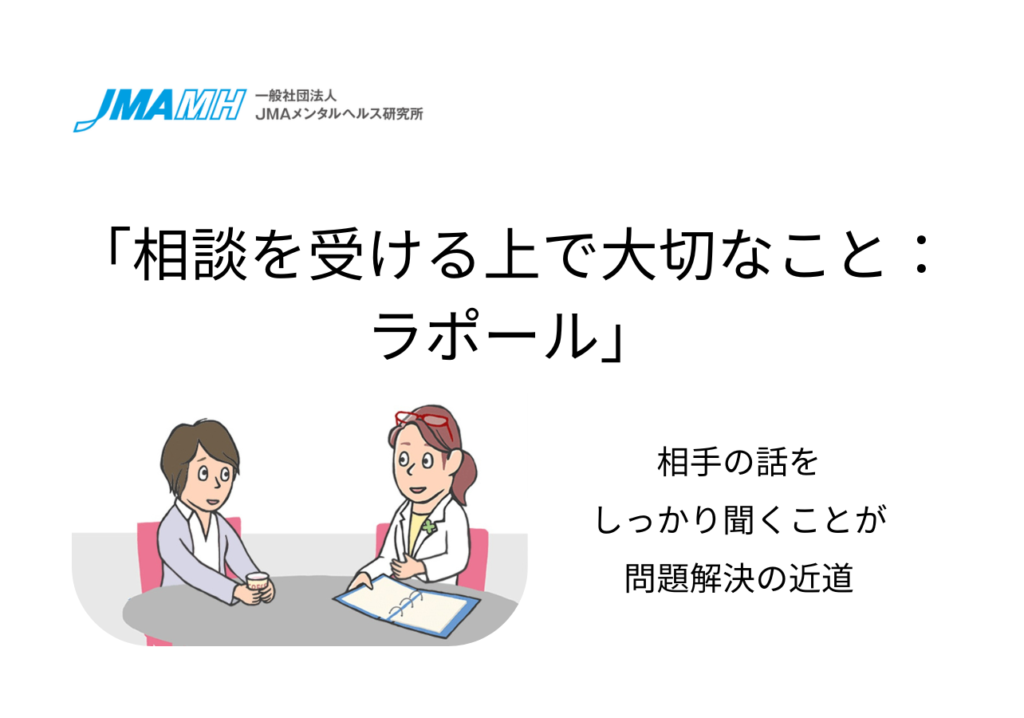
最近はAIをカウンセリングに使う試みが始まっています。私も先日ChatGPTに“とてもつらいことがありました”と試しに入力してみたところ、「それは大変でしたね。もし話したい気持ちがあれば、どうしたことがあったのか教えてもらえますか?」と返ってきました。相談者のつらい気持ちに共感し、“つらかった話を聞きますよ”という姿勢を示すことは、まさしく心理面接と同様です。どうやらAIも、カウンセリングの基本をきちんと学んでいるようです。
私は心理師として様々な方の相談にのっていますが、その中で大切にしていることは『ラポール』です。
ラポールは、『心理療法場面の(中略)相互的・共感的・受容的な関係性』のことであり、平たく言えば「この人なら分かってくれる」「この人は私のことを傷つけない」とクライエントが感じることができるカウンセラーとの関係性のことです。
小さな悩み相談を受けるにしても、かっちりした心理療法を実施するにしても、ラポールを形成することは基本かつ重要なことです。ラポールは測定するのが難しいため、研究の対象になることがありませんでしたが、近年ようやく注目され始め、ラポールが心理療法の効果に大きな影響を与えていることが分かってきています。
相談に来られる方々は、「このことで困っています」「これが幸いのでなんとかしたいです」と解決策を求めていらっしゃることが多いと思います。ですので、相談された側は“困っていることをなんとか解決しなくては”という気持ちになり、「そんな時はこうしたらいいですよ」「その問題についてはこうしてみましょう」とアドバイスしたくなります。しかし、その提案したくなる気持ちをぐっと抑えて、まずはラポールを築いてしっかりと相手の話を聞く、ということがなによりも大切です。
私がまだ駆け出しの心理師だった頃、ある方から子育てについての相談を受けました。子供の状態を伝えてかかわり方をアドバイスしましたが、次の回もその次の回も、私のアドバイスを全く実行に移してくれませんでした。私はアドバイスがしずらくなり、傾聴しかできなくなってしまいました。何度か回数を重ねてお互いに信頼し合えた頃、話の流れで初回と同じようなアドバイスをしたところ、次の回にはそのアドバイスを実行してくださいました。その時私は「前も言ったのに」と思いましたが、今思えば、初めの頃は私への信頼感がなく、アドバイスを実行しようという気持ちになれなかったのだろうと思います。傾聴しかできないのではなく、傾聴してラポールを築くことがこの方の行動を変えるのには必要だったということが、今ではよくわかります。
相談に来る方々は、どのような人が相談に乗ってくれるかも分からず、不安な気持ちを抱えて相談にやってきます。自分の問題は解決できるのか、「そんな些細なことで相談しにきたのか」と叱責されやしないか、と様々なことが頭に浮かびつつも、勇気を出して相談に来ています。そのような時は、「大変でしたね」「相談してくれてよかったです」という言葉を聞くだけでも気持ちが楽になりますし、「この人なら私の辛さを分かってくれるだろう」という安心感も芽生えます。そのような関係性ができてこそ、相手のアドバイスを信じることができますし、「この人が提案してくれたことをやれば、問題が解決するかもしれない」という期待感を持つことができます。心理的に安心できて始めて、ご自身の問題に向き合うことができるのです。
総務や人事など、仕事上で相談にかかわる方にぜひ知っておいていただきたいのは、初回の面談は、「また困った時に、この人に相談したい」「相談してよかった」と相談に来た方に思ってもらうことが第一目標だということです。
クライエントの心の準備が整わなければ、「相談」は成立しません。もちろん、働いている場所や職種、状況によっては、そんな悠長なことを言っていられない場合もあるかもしれません。それでも、ぜひ「ラポール」を意識することが問題解決の近道であるということを、心のどこかに留めておいていただければと思います。
執筆者:木ノ内(小澤)満玲(公認心理師・臨床心理士)
参考文献:
斯波・佐野(2002)『ラポール形成』に関する研究の展望 教育相談研究 40, 61-66
小川瑛(2019) 心理臨床家の経験知に基づくラポールの定義について 立教大学臨床心理学研究 13,15-24