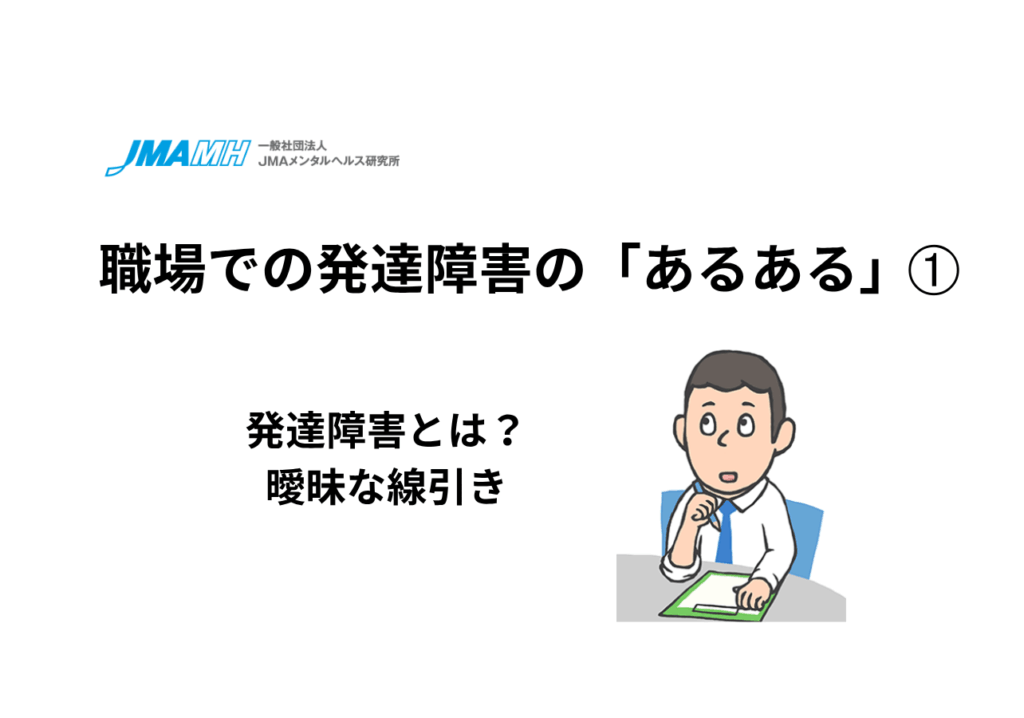
突然ですが、みなさんは“Neurotypical Disorder”という新種の病をご存じでしょうか。その特徴をいくつか挙げてみましょう。
・他者の感情を感じることができる
・他者との過剰な接触を求める
・みんなと遊ぶことにこだわり、一人遊びができないことがある
・他者とのコミュニケーションをする際に、視線・表情・しぐさなどを多用する傾向がある
・感情に合わせて不必要に声の調子を変えたり、もしくは声の調子を不必要にコントロールしようしたりする傾向がある
・嬉しくないプレゼントをもらった時に「ありがとう」と言うなど、言葉を意味の通り、正しく使うことができない
・嘘を使うこともある
・機能性がないにもかかわらず、それにこだわったりすることがある
・たとえば、物が順番に並んでいない、整列していないなど、物事の細部を気にしたり気づいたりすることができない
この病は、なんと98%の人があてはまると言われています。さて、どんな病であるか分かりましたか?
列挙した特徴をお読みになって気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、これは“定型発達症候群”、つまり「定型な発達をしてきた人たち=発達が障害されていない人たち=発達障害と言われない人たち」のことを記述したものです。実際に“定型発達症候群”という診断名があるわけではありませんが、このように“定型発達”の特徴を表現すると、それはそうだけれど、本当にそれは問題ではないのか?という気持ちになってきます。きっと、何が問題で何が問題ではないのかということは、線がきちんと引けるものではなく、非常に曖昧で、状況に依存しているものなのでしょう。
近年『発達障害』『ADHD』『アスペルガー症候群(現在は自閉スペクトラム症に含まれます)』といった言葉が認知され、「ちょっと変わっている」方々に名前が付き始めました。精神疾患の病名というのは、DSMやICDなどの診断分類によって診断されます。しかし、統計データの数値の変化や最新研究で明らかとなった事実によってアップデートされていくため、その分類は永続的なものではなく、細かい部分が変わることがあります。
発達障害は、前頭葉44野の容量が小さかったり、ミラーニューロンといった神経細胞群の活性が低かったりするなど、生得的に脳機能に偏りがある脳機能障害です。しかし、すべての人に診断名が付くわけではなく、環境に恵まれていたり本人の適用に問題がなかったりすれば、発達障害と診断されることなく、普通に自立した社会生活を送っている場合もあります。
私は心理師なので診断をすることはありません。ですので、私がお会いする方々は、診断名がついている場合もありますし、ついていない場合もあります。そして、ご本人がご自身の症状で困っている場合だけでなく、周囲の方々が対応に困って相談にいらっしゃる場合もあります。次回は、これまで受けた相談をもとに、職場における発達障害の“あるある”とその対処法について、お話していこうと思います。
執筆者:木ノ内(小澤)満玲(公認心理師・臨床心理士)
参考文献:
備瀬哲弘監修(2013).「ちゃんと知りたい―大人の発達障害がわかる本」.洋泉社.
千住淳(2014).「自閉症スペクトラムとは何か―ひとの「関わり」の謎に挑む」.筑摩書房.
岩波明(2015).「大人のADHD―もっと身近な発達障害」.ちくま新書.
佐々木淳(2024).「こころのやまいのとらえかた」.ちとせプレス.