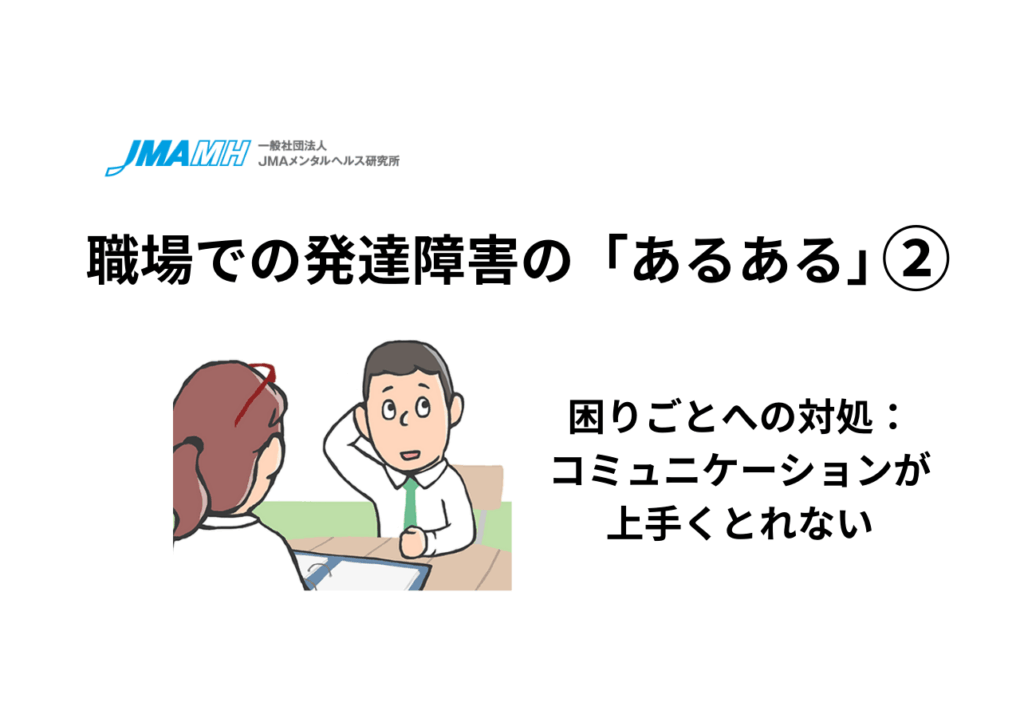
前回は、発達障害が脳機能障害であることについて簡単にご説明しました。発達障害関連の本はたくさん世に出ていますので、ADHDや自閉スペクトラム症の特徴に関しては、そちらを参考にしていただければと思います。今回は、職場における発達障害の“あるある”とその対処法について、お話させていただきます。
発達障害は、子供のうちに見つけられるものだと思われがちですが、「単純なミスを繰り返す」「人間関係が上手くいかない」といったことで、大人になってから診断される方も増えています。もし、ご本人自身が何かしらの生きにくさを感じているようであれば、産業医や健康管理相談窓口に行ってみる(周囲から勧めても良いでしょう)のも一つの手ですし、そこから専門医の診察を受けて困りごとに対するアドバイスをもらうと、仕事がしやすくなるでしょう。しかし、本人はそのつもりがないけれど周囲が困っている、または、性格の問題なのか特性の問題なのか判断がつかない、といったこともよく生じています。
発達障害は、たとえ診断名がついていても、どのような特性があるのか、どの程度の特性があるのかについては個人によって異なります。また、環境によってもその表われ方は様々です。
対策を考えるためのコツは、「何に困っていて、どのような状況でそれが生じるのか、どのような状態になればよいのか」について、細かく丁寧に整理することです。
では、いくつかの例を具体的に考えてみましょう。
①コミュニケーションが上手くとれない
“コミュニケーション”と一概にいっても、話し出すと止まらない、話がとぶ、話に割り込む、場にそぐわない発言がある、強引で威圧的・・・など状態は多様です。そして、それが不注意や衝動の問題で、分かっているけれど止められないのか、相手の表情や文脈が分からないからやってしまうのか、ということも細かく見ていく必要があります。そして、多くの場合、「どうして伝わらないんだろう」と周囲が思っている時は、ご本人も「どうして伝わらないんだろう」と思っています。お互いに困っているため、溝が深まりやすいのです。
たとえば、「話し出すと止まらない」ということについて考えてみましょう。衝動をコントロールするのに困難さがある場合には、思いついたことをすぐに言わずにはいられないことが原因になります。一方で、相手の表情が読めなかったり、話しても良い状況なのかの認識ができていなかったりすると、興味のある分野の話を一方的にし続けてしまいます。
そして、そのことによって、何が問題になっているのでしょうか。指示が伝わらず仕事が進まないのでしょうか。取引先との関係が悪化してしまうのでしょうか。相手が何を考えているのか分からずに不安なのでしょうか。なにが問題で、どういう状態になれば状況が好転するのかということをイメージしてみると、本人自身で工夫できること、周囲がサポートできることが具体的になっていきます。
もし「指示をしている途中で話がそれて指示が明確に伝わらない。指示通りに作業をしてほしい」のであれば、ご本人は、話す前に一呼吸おくようにする、話したい衝動が抑えられないのであれば「すみません、今思ったことを言ってもいいですか?」と前置きを言って状況を確認するようにするといった方法が考えられます。周囲は、指示を端的に伝え、対話を短くすると良いかもしれません。
「取引先において対話の最中に関係のない話を急にし始めるので、取引先からクレームがきている。取引先の関係修復を図りたい」のであれば、本人は、自分の話ではなく相手について(とくに長所)を話題にするよう心がけるといったコミュニケーションのコツを学ぶ必要がありますし、周囲は具体的に「誰にどのような口調で話すべきか」ということを指導したり、適材適所を考えて、取引先に関わる必要がなく一人で担当できる業務を割り振ったりするのもよいかもしれません。
次回は、②スケジュール管理が苦手な場合、についてお伝えしていきます。
執筆者:木ノ内(小澤)満玲(公認心理師・臨床心理士)
参考文献:
備瀬哲弘監修(2013).「ちゃんと知りたい―大人の発達障害がわかる本」.洋泉社.
千住淳(2014).「自閉症スペクトラムとは何か―ひとの「関わり」の謎に挑む」.筑摩書房.
岩波明(2015).「大人のADHD―もっと身近な発達障害」.ちくま新書.
佐々木淳(2024).「こころのやまいのとらえかた」.ちとせプレス.
シリーズコラム一覧はこちら▼
職場での発達障害の「あるある」① 発達障害とは?曖昧な線引き
職場での発達障害の「あるある」③ 困りごとへの対処:スケジュール管理が苦手
職場での発達障害の「あるある」④ 困りごとへの対処:周りが気になり落ち着きがない